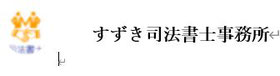相続
相続が発生するとどのような手続きを行うのか、長期間放置していた相続手続きを行いたい、生前に相続対策を行いたいなど、お客様のご要望に沿えるように考えさせていただきます。
不動産の名義変更(相続登記)はもちろん、相続放棄など裁判所提出書類作成などもご相談ください。
相続とは
相続とは死亡した人(被相続人)の権利義務を被相続人の親族関係にある者(相続人)が引き継ぐことです。承継させるのは預貯金や不動産などの積極財産だけでなく、借金などの債務(消極財産)も含まれます。
相続人になるのは、被相続人の①子、②直系尊属(父母、祖父母など)、③兄弟姉妹です。その順位は①、②、③ですが、配偶者はどの場合も相続人になります。①の子は数人いれば全て相続人となります。実子、養子に差はありません。②の直系尊属は父母と祖父母がいれば父母が相続人になります。実親と養親に差はありません。③の兄弟姉妹は父母の双方が同じ兄弟姉妹と父母の一方が同じ兄弟姉妹が含まれます。
相続人になるはずの人が被相続人より前に亡くなった場合は、相続人の範囲が変わります。これを代襲相続といいます。子が被相続人より前に亡くなった場合は、その者の子(被相続人にとっては孫)が代襲し、相続人となります。代襲すべき者が被相続人より前に亡くなった場合は、その者の子(被相続人にとっては曽孫)が再代襲し、相続人となります。兄弟姉妹が被相続人より前に亡くなった場合は、その者の子(被相続人にとっては甥、姪)が代襲して相続人になります。被相続人の甥、姪は再代襲しません。
被相続人の死亡により発生した相続手続きが未了のうちに、相続人の一部が死亡にして新たな相続が発生した場合も相続人の範囲が変わります。これを数次相続といいます。例えば被相続人がAでその相続人がBとCである場合、相続手続きが未了のうちにCが死亡した場合はBとCの相続人が相続手続きを行います。
積極財産と消極財産の承継には3つの方法があります。単純承認、限定承認、相続放棄です。単純承認とは、積極財産と消極財産の全てを承継することをいいます。相続が発生し、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に限定承認や相続放棄の手続きをとらなければ単純承認となります。限定承認は、積極財産の範囲で消極財産も承継することです。相続放棄とは、消極財産が積極財産より多い場合などに全てを承継しない手続きです。
相続手続きを進めるにあたり、はじめに積極財産、消極財産、相続人を調べることが必要です。
①単純承認
積極財産、消極財産とも全て承継する。
単純承認とみなされる行為
・相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
例 不動産や動産の売却、贈与 被相続人の債権の取り立て
・遺産分割協議を行うこと
・相続人が自己のために相続が発生したことを知ってから3か月以内に限定承認や相続放棄の手続きを行わなかったとき
・限定承認や相続放棄をした後であっても相続財産の全部または一部を隠したり、財産目録に記載しなかったとき
単純承認とみなされない行為
・死亡保険金や遺族年金の受け取り
・被相続人名義の家屋の修繕
・少額の形見分け
・5年を超えない土地の賃貸借(樹木の植栽又は伐採を目的とする山林の賃貸借は10年を超えないもの)
・3年を超えない建物の賃貸借
②限定承認
積極財産の範囲で消極財産も承継する。
・被相続人に借金がある場合で、その額が不明な場合
・被相続人が保証人になっているかもしれない場合
・形見分けを受けたい財産がある場合
・相続開始後3か月以内に相続人全員で家庭裁判所に申し立てをする必要がある。
③相続放棄
積極財産と消極財産の全てを承継しない。
・消極財産が積極財産より多い場合
・相続人ごとに自己のために相続があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要がある。
相続が発生したときに行うこと
①積極財産の調査
・不動産は固定資産税納税通知書や名寄帳で調べることができます。
・預貯金は通帳、キャッシュカード、金融機関からの郵便物などで確認できます。
・有価証券は証券会社からの郵便物などで確認できます。
②消極財産の調査
・金融機関からの借入は信用情報機関から信用情報を取り寄せて調べることができます。
・信用情報に記載されない負債や、保証人になっているか否かについては被相続人が残した契約書や郵便物などから調べます。
・金額が不明な借金がある、保証人になっているかもしれない場合は相続放棄や限定承認を検討します。
③相続人の調査
・亡くなられた人(被相続人)の相続人を確定するために戸籍を収集します。被相続人の出生から死亡までの戸籍及び相続人の戸籍を収集します。
・代襲相続の場合は、被代襲者の出生から死亡までの戸籍と代襲相続人全員の戸籍も必要です。
・数次相続の場合は、死亡した相続人の出生から死亡までの戸籍とその者の相続人の戸籍も必要です。
④遺言の有無の調査
・遺言の有無によりその後の手続きが変わります。主に利用されている遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
・自筆証書遺言の場合には家庭裁判所の検認の手続きをしてからその内容に従って名義変更をします。令和2年7月10日から法務局における自筆証書遺言の保管制度が始まりました。法務局に預けている自筆証書遺言は検認の手続きは不要です。
・公正証書遺言の場合は検認の手続きは不要であり、その内容に従って名義変更をすることできます。公正証書遺言の有無は公証役場に問い合わせることができます。
・遺言が無い場合は、相続人全員で遺産分割協議をして遺産分割協議書を作成します。
現在使用されている遺言には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
・自筆証書遺言
自筆証書遺言は、自書能力が備わっていれば他人の力を借りることなく、いつでも自らの意志に従って作成することができます。日付と氏名を自書し、押印が必要です。本文と財産目録の全文の自書が必要でしたが、平成31年1月13日から財産目録についてはパソコンで作成することができるようになりました。また財産目録として預貯金のコピーや登記事項証明書を用いることができます。令和2年7月10日から法務局における自筆証書遺言の保管制度が始まりました。
・公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人の関与の下で、2人以上の証人が立ち会うなど厳格な方式に従って作成され、公証人がその原本を厳重に保管するという信頼性の高い制度です。また、遺言者は、遺言の内容について公証人の助言を受けることができます。また、遺言能力の確認なども行われます。
⑤遺産分割協議
・遺産分割協議とは相続人全員で遺産(積極財産)をどのように相続するか決めることです。相続人が未成年者の場合はその親権者が代わりに遺産分割協議を行いますが、親権者も相続人の場合は特別代理人を選任して遺産分割協議を行います。
・遺言がある場合や、法定相続分に従って相続する場合には遺産分割協議は不要です。
・遺産分割の内容が決まったら遺産分割協議書を作成します。相続人全員の署名と実印による押印をします。印鑑証明書も添付します。遺産分割協議書は不動産や預貯金の名義変更に必要です。
・遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することができます。
⑥名義変更
・預貯金や有価証券の名義変更は戸籍、遺言書または遺産分割協議書が必要です。関係機関ごとに必要な書類もありますのでご確認ください。
・平成29年の法改正により法定相続証明情報の制度が開始されました。この制度では法定相続情報一覧図を作成して法務局に認証してもらうことができます。預貯金や有価証券の名義変更がある場合は、法定相続情報一覧図を作成することをお勧めします。
・不動産は相続登記を申請します。
相続登記
・2023年から相続登記が義務化される予定です。
相続登記を放置した場合のデメリットとして次のことが考えられます。
・相続登記を完了する前に相続人のなかで亡くなった人がいる場合(数次相続)
この場合、亡くなられた相続人の相続人が遺産分割協議に加わる必要があります。
例えば、相続人が配偶者と子の場合で、相続手続きを放置している間に子が死亡した場合、子の相続人も当初の相続の遺産分割協議に加わる必要があります。親族関係も疎遠になり、遺産分割協議が困難になることも考えられます。
・不動産を売却したい場合や不動産を担保に融資を受けたい場合
不動産の名義人が死亡した人の場合は、相続登記をしなければ売却できません。融資を受けるために担保を設定することもできません。

民法(相続法)改正
1. 配偶者居住権の新設(2020年4月1日施行)
・配偶者短期居住権
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合、遺産分割が終了するなど一定の期間、その建物を無償で使用することができます。
・配偶者居住権
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合、遺産分割協議、遺贈などにより配偶者居住権を取得することができます。
配偶者居住権のメリット
・配偶者は終身または一定期間、無償で建物に居住することができる
・配偶者居住権は土地・建物の所有権より評価額が小さいため、配偶者が預貯金等の他の遺産を取得することができる。
・配偶者居住権は登記することができるため、第三者に自分の権利を主張することができる。
2. 婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置
(2019年7月1日施行)
婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物またはその敷地)の遺贈又は贈与がされた場合は、遺産分割ではその分を特別受益として扱わずに相続分を計算することができます。つまり、過去に贈与を受けたことには関係なしで遺産を取得することができます。
3. 遺産分割前の預貯金の払戻し制度(2019年7月1日施行)
家庭裁判所の審判なしで預貯金の払戻しができる制度と家庭裁判所の審判が必要な制度があります。
・家庭裁判所の審判なしで払戻しができる制度
払戻しができる金額
(相続開始時の預貯金債権の額(口座基準))× 1/3 (当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分)
ただし、1つの金融機関から払戻しが受けられるのは150万円まで
被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、払戻しを受ける者の印鑑証明書を提出します。
払い戻しを受けた者が遺産の一部分割によりこれを取得したものとみなされます。
・家庭裁判所の審判を経て払戻しができる制度
相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁など家庭裁判所が遺産に属する預貯金債権を行使する必要があると判断する場合に認められます。
4. 自筆証書遺言の方式緩和(2019年1月13日施行)
・全文、日付、氏名は自書し、押印する。
・財産目録については自書することを要しない。パソコンで作成することも可能。登記事項証明書や通帳のコピーを財産目録として使用できます。
・財産目録の毎葉に署名・押印(両面の場合は両面に署名・押印)
・同一の用紙に本文と印刷目録の混在はさせない。(裏面、空白箇所の使用も不可。別紙にする。)
・財産目録は自筆証書と一体のものとして添付する。

「Q&A」
Q1 本文と財産目録を編纂(ホッチキスどめ等)する必要があるか。
A、必要ありません。
Q2 目録と自筆証書遺言の本文を記載した葉とを綴る際に契印をしなければならないか。
A、必要ありません。
Q3 目録に押印する印鑑は登録した印鑑をもってしなければならないか。自筆証書遺言の本文に押印した印鑑と同じものである必要があるか。
A、登録された印鑑である必要はありません。同じ印鑑である必要はありません。
Q4 ワープロで作成した目録に自筆証書遺言の本文を手書きで書き加えることはできるか。
A、できません。
Q5 既に作成した遺言のうち、財産目録(の部分)を破棄して新しい財産目録を添付することで、自書によらない財産目録の差し替えをしたい。このような差し替えが認められるか
A、認められません。
5. 法務局における自筆証書遺言の保管制度(2020年7月10日施行)
遺言者が、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(法務大臣の指定する法務局)において、自筆証書遺言に係る遺言書の保管を申請することができるとする制度です。保管される遺言書は、封のされていない法務省令で定める様式に従って作成されたものです。遺言書保管所に保管されている遺言書については、家庭裁判所の検認が不要です。
遺言者死亡後に相続人や受遺者ができること
・遺言書が保管されているか調べること(遺言書保管事実証明書の交付請求)
・遺言書の写し交付請求(遺言書情報証明書の交付請求)
・保管されている遺言書の閲覧
遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付請求がされると、遺言書保管官は、他の相続人等に対し、遺言書を保管している旨を通知します。
6. 遺留分の制度(2019年7月1日施行)
遺留分とは兄弟姉妹以外の相続人が取得することができる、遺産の最低限の取得分をいいます。法改正前は、遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求をして、侵害額相当の不動産の持分の取得をしました。その結果、不動産が共有状態になり、その後の処分が困難になりました。この制度が見直され、遺留分を損害された相続人は、遺留分侵害額請求をすることができるようになりました。
遺留分侵害額請求
・遺留分を侵害された相続人は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができる。
・遺留分侵害額請求の対象となる生前贈与は(イ)第三者に対する贈与は相続開始1年以内のもの、(イ)相続人に対する贈与は相続開始前10年以内の、婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与(特別受益)
・相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内、かつ、相続開始から10年以内に行使する必要があります。
・遺留分侵害額請求を受けた者が直ちに金銭を準部できない場合は、裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることができます。
7. 特別の寄与の制度(2019年7月1日施行)
・この制度を利用できるのは、被相続人の親族で相続人以外の者です。
・この制度を利用するのには次のことが必要です。
被相続人の生前に労務の提供・療養看護、その他の労務の提供による財産の維持又は増加についての特別の寄与があった場合です。
・遺産を取得した相続人に対して、寄与分に相当する金銭の請求をすることができます。
・相続の開始及び相続人を知った時から6か月以内、かつ、相続開始の時から1年以内に権利を行使する必要があります。